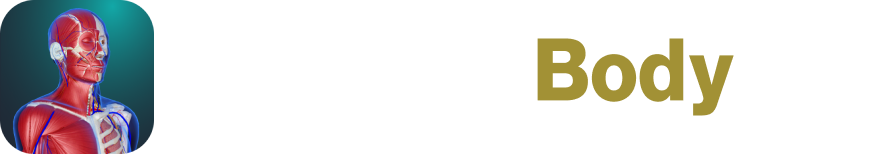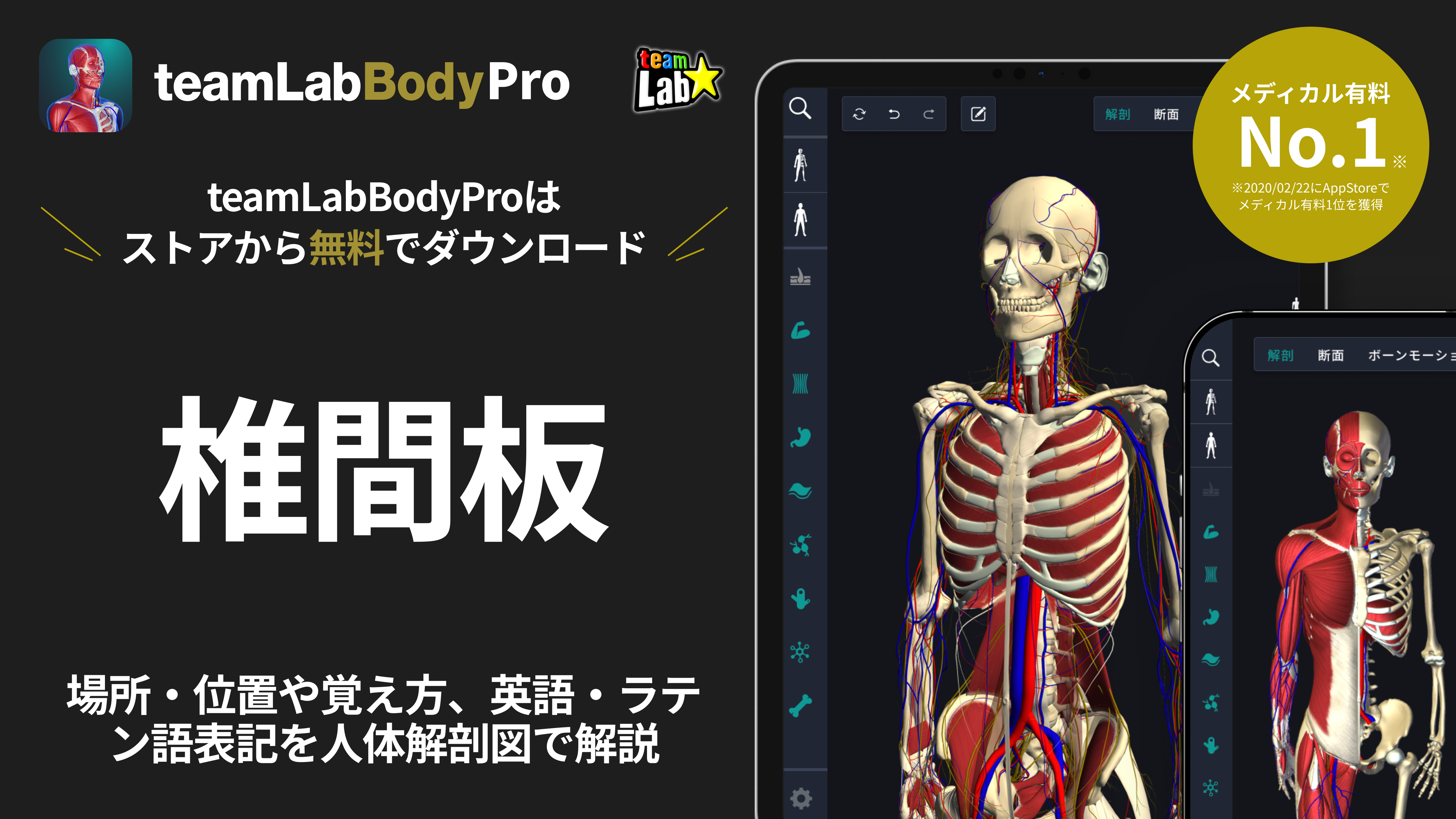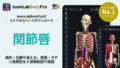はじめに
本記事では「椎間板」について詳しく解説します。
椎間板は背骨の間に位置し、体がスムーズに動けるよう、クッションの役割をしています。しかし、柔らかいために損傷しやすく、椎間板ヘルニアのようなトラブルをしばしば引き起こします。椎間板の中心には核(核髄)という部分があり、この部分が圧力をうまく吸収・分散しています。ですが、年齢を重ねたり悪い姿勢を続けると、核髄の機能が落ち、椎間板が変形したりヘルニアになるリスクが上がります。そのため、椎間板と核髄を健康に保つには、適切な姿勢と運動が必要です。
本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。
椎間板(ついかんばん)に関する動画の視聴はこちらから
チームラボボディPro 無料ダウンロード
人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ
チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

椎間板とは
椎間板は、脊椎骨の間に存在するクッションのような組織のことを指します。この組織は軟骨によって構成され、柔軟性が非常に高いです。背骨が硬い骨だけでできていたら、柔軟に動くことはできませんが、椎間板のおかげで、左右や前後に自由自在に体を動かすことができます。
椎間板の読み方
椎間板の正しい読み方は「ついかんばん」です。
椎間板の特徴
椎間板は非常に高い柔軟性が特徴です。しかし、柔軟性の高さの裏では、重みに耐えきれずに損傷しやすい側面もあります。そのため、椎間板ヘルニアなどのリスクも存在します。
椎間板の場所・位置

椎間板は、首から腰にかけて脊椎骨の間に位置しています。これらは頸椎、胸椎、腰椎の各部にわたって配置され、骨と骨の間で柔軟なクッションの役割を果たしています。
椎間板の覚え方
「椎骨と椎骨の間の柔らかなクッション」と覚えましょう。このイメージは、椎間板の位置と特徴を表しています。
椎間板の英語・ラテン語
英語で椎間板は「Intervertebral Disc」、ラテン語では「Discus intervertebralis」と表されます。「脊椎の骨間にある円盤」という意味がこめられています。
椎間板の豆知識
椎間板を傷めないためには、正しい姿勢が極めて重要です。適切な運動や正しい持ち上げ方など、日常生活の中で椎間板を保護し健康を保ちましょう。
椎間板に関連する組織:核の特徴
椎間板の中心にある核は正式には「核髄」と呼ばれ、主に水分とプロテオグリカンで構成されています。この核髄はゼリー状の物質で、椎骨間にかかる圧力を吸収して分散させる役割を持っています。核髄が健康な状態であればあるほど、椎間板はそのクッション機能を最大限に発揮し、脊椎の柔軟性と安定性を保つことができます。しかし、加齢や過度の使用、不適切な姿勢などによって核髄内の水分が減少し、プロテオグリカンの構成が変化すると、核の機能は低下します。これは、椎間板の変性やヘルニアの原因にもなりうるため、核髄の健康が脊椎全体の健康に直結していると言えるでしょう。
椎間板に関連する組織:核の場所・位置
核髄は椎間板の中央に位置しており、周囲を繊維輪と呼ばれる繊維質の組織で囲まれています。この繊維輪は、核髄が過剰な圧力を受けた際に外側へ流出するのを防ぐ役割を持っています。椎間板自体は、脊椎を形成する各部位、つまり頸部から胸部、腰部、そして仙骨部にわたって存在しています。
核髄の位置は椎間板が健康な状態では、椎間板の中央にありますが、椎間板が変形したり、圧力が片側に偏ったりすると、核が片寄り、最終的には繊維輪を突き破ってしまい、椎間板ヘルニアを引き起こします。
椎間板に関連する組織:核の豆知識
核髄は生まれた時点での水分含有量が最も高く、加齢と共にその水分量は減少していきます。これは、老化による椎間板の変形の主な理由の一つです。さらに核髄の水分は一日のうちで変動します。起きて活動している間、椎間板には圧力がかかり、徐々に水分が押し出されます。これにより、日中は身長がわずかに縮んできます。逆に、横になって休息していると、核髄は再び水分を吸収し、身長が回復します。
椎間板のクイズと正答
Q:椎間板は英語で何というでしょう?
A:Intervertebral Disc
まとめ
今回は「椎間板」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。
学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!
ぜひ、次回のブログもお楽しみに。
解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!
teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。
複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。
今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。
チームラボボディPro 無料ダウンロード
人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ
チームラボボディProのダウンロードはこちらから!